| 幸 せ の 意 味 を 探 し て | |||
| 〜 第二話 『 疑 似 餌 』 〜 | |||
昔からよくある怪談話し。 旧校舎のトイレには、小学生の少女が出て来る。 美術室にかけられている絵の目が動く。 音楽室で、ピアノの音が聞こえる。 などなど。 その学校にある伝統にも似た、多種多様なお話ばかりだ。 話しのほとんどが、目の錯覚だったり。 風のいたずらだったりする。 だが、ごく希に本物も存在する。 実際に幽霊は存在する。 それは水先案内人のぼたんはよく知る所だ。 自分の仕事が、その「幽霊」を導く役目をしているのだから。 クラスの女子数人で輪になって薄くらい教室で、そんな怪談話しをしていた。 転校したてのぼたんからすれば、初めて聞く話しばかりで、楽しそうに耳を傾けていた。 水先案内人同士、休憩室でこんな風に話しはする。 だが、何丁目の誰さんがそろそろお迎えだ・・・とか。 なんとかさんを連れて行った時に、苦労した・・・とか。 そんな話しが普通。 こんな風に、年相応の話しと言うのに憧れていた部分もあった。 この学校に来れて、一番嬉しい事の一つでもある。 ぼたんは、興味津々に次々と友達からの話しを聞いて回っていた。 「ぼたんちゃんって、怪談話し好きなんだね。」 「うーん、あ、ほら!怖いもの見たさってヤツさね。」 「あーわかる♪わかる♪」 きゃっきゃっと騒いでいる。 すでに最終下校時刻まで、時間がない。 話しを一段落して、それぞれが帰り支度を始めた。 無論、ぼたんも同じくカバンに教科書を詰め込んで、席を立ち上がろうとした時だった。 『助けて。』 ふと、そんな声が聞こえた気がした。 ぼたんは声のした方へと視線を向けた。 『助けて。』 今度はハッキリとした声で、ぼたんの耳に届いた。 高校だと言うのに、あまりにも子供じみた声。 それは、人間のものではなく、確実に霊気から発せられた声。 ぼたんはカバンを手にすると、先程まで一緒に話していた友達に突然に別れを告げた。 「え、ぼたんちゃん!駅前のバーガー食べに行かないの!?」 「ごめーん!また、今度ねー!」 そんな風に言いながら、ぼたんが向かった先は下駄箱とは正反対の方向。 クラスメイトは、顔を見合わせながらぼたんの後姿を見つめた。 「ねぇ、あっちってさ。」 「うん・・・旧校舎の方だよね。」 「「何の用事があるんだろう?」」 今は使われていない、旧校舎。 そちらへと向かって行ったぼたんを不思議に思いつつも、下校する事にした。 「それにしても、ぼたんちゃん置いてきちゃって大丈夫なのかなぁ?」 「うん。でも先に帰ってて、言ってたし。」 「ぼたんちゃんって霊感とかあるのかな?」 ふと『ぼたん』の名前が耳に入って、蔵馬は目の前を見つめた。 少し離れた所には、クラスメイトが数人歩いていた。 たしか放課後にぼたんと共に話していた集団だ。 蔵馬は、少しだけ歩く速度を速めると彼女たちの後へとついた。 「水先さんがどうかしたの?」 「きゃっ!」 別に驚かせるつもりはなかったが、突然話しかけられて、女子達は異様な程に過剰反応を示した。 その反応を見て、蔵馬はふと嫌な事が過ぎった。 「驚かせてしまって、すみません。」 「南野君か〜、びっくりしたぁ。」 一同に胸をなで下ろす仕草に、蔵馬は首を傾けた。 そんなに暗い訳でもない。 部活を終えて、下校途中に会っただけだと言うのに、異様な恐がり方。 もしかして。 「怪談話しでもしてたんですか?」 「えーどうしてわかっちゃうの〜。さすが南野君だよねー。」 やっぱり。 彼女たちの周りにいる異様な数の妖怪や幽霊はその為か。 蔵馬は、近くに群がる者達に一瞥すると同時に妖気を少しだけ放った。 それを感じた瞬間に、周りにいた雑魚と言える妖怪達は一目さんに逃げて行った。 まったく。 何も知らないと言うのも怖いものですね。 蔵馬はそんな事を頭に思い浮かべながら、内心苦笑していた。 見えなくて幸せとは、この事を言うのだろう。 もう一度クラスメイトの顔ぶれを見て、蔵馬は再度質問した。 「水先さんは、一緒じゃなかったんですか?」 「あーそれがねぇ、なんか用事があるとかで、旧校舎の方に突然走り出しちゃったんだよねー。」 「え?旧校舎に?」 蔵馬が少し驚いて聞き返すと、女子達は一応に怖がる素振りを見せ始めた。 だが、蔵馬の耳には少しも入っていなかった。 ぼたんが旧校舎に何の用事があるのか。 あるとすればひとつだけ。 はぐれた魂を見つけたか・・・もしくは、妖怪の触手に触れたか。 妖怪・・・。 「!!」 蔵馬は、慌てたように振り返った。 旧校舎と言えば学校内でも、黒い噂の絶えない場所だ。 取り壊そうにも、業者が入れないと言っていた。 それほどな場所。 蔵馬からすれば、さほど危険な場所と言うわけでもないのだが。 ぼたんならばどうなのだろうか。 人間の妖怪化を抑える事が出来る程の高等心霊医術の持ち主と言う事は、それ相応の霊気の持ち主。 妖怪にとっては、格好の餌。 餌・・・。 蔵馬は頭で考えるよりも先に、体が動いていた。 後で、クラスメイトが名前を呼んでいたが、それに答える余裕はなかった。 ただひたすらに、学校への道を戻った。 ひたすら走る事しか出来ない自分。 人間である自分がもどかしい。 初めて蔵馬は、そう実感した。 何故だか、わからないが。 そう感じた。 学校まで戻った蔵馬の目の前に映ったのは、いつもの学校とは逸していた。 不気味な程な、赤黒い空。 すでに門は閉まっており、人がいる気配はない。 ただ、禍々しい妖気だけが渦巻いていた。 「・・・本当に、厄介な人ですね。」 蔵馬は一言呟くと、軽々と校門を飛び越えて、中へと入った。 中に入った途端に、感じる違和感。 身を切るような感覚。 蔵馬は一度、大きく息を吐き出した。 どう見ても、異常事態としか思えない。 蔵馬はゆっくりと旧校舎へと足を向けた。 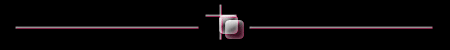 『助けて。助けて。』 ぼたんは慎重に旧校舎の中へと足を踏み込んだ。 むせ返るような、充満した妖気の中に、小さな霊気を感じる。 どう見ても、迷い魂。 しかも妖怪に捕らわれているとしか思えない。 ぼたんは周りを注意深く探りながら、声が強く聞こえる方へと足を向けた。 「誰かいるのかい!?」 大きな声で叫んだ瞬間。 先程まで感じていたむせ返るような妖気が一瞬にして消えた。 息苦しかった感覚から、一瞬だけ解放される。 自然とぼたんは大きく息を吐き出した。 『助けて、おねーちゃん。』 「どこにいるんだい!?」 ぼたんは階段を見上げた。 どうやら上の階から聞こえるようだ。 なんとなく、後を振り返れば、そんなに遠くない入り口が、まるで遙か彼方にあるように思えた。 まだ、引き返しはきく。 そんな警告が頭の中で響く。 でも。 あんな小さい子がもしも迷っているのであれば、助けなくては。 ぼたんは、決心したように階段に一歩足をかけた時だった。 「貴様、ここで何をしている。」 「ぎゃーーーーー!!!!!」 急に声をかけられたぼたんは、飛び上がる程に驚いた。 ゆっくりと振り返れば、誰もいない。 そこで視線を少しだけ下へとずらすと。 ムスっとした顔の飛影がそこに立っていた。 「ひ…飛影じゃないか…脅かさないでおくれよ。」 「何をしてるのかと聞いてる、女。」 「女じゃんくて、ぼ・た・ん!!」 チャキッっと愛刀をぼたんの首筋へと宛がった。 その見事な程の刃を横目でみつつ、ぼたんは生唾を飲み込んだ。 このまま斬られてしまうんじゃないかって思う程の、殺気を飛影から感じる。 飛影ならば、一瞬の出来事。 そして、何も感じないはずだ。 幸いな事は、彼は今、霊界裁判において執行猶予の身と言う事。 おいそれと霊界の女・・・しかも霊界探偵の助手を殺そうとはしないだろう。 「飛影こそ、こんな所で何してるのさ。」 「チッ。貴様も嫌なヤツと同類か?」 「嫌なヤツ?」 「質問を質問で返すヤツの事だ。」 誰の事を言ってるのだろうか? ぼたんは意味がわからないと、首を傾げた。 『助けて、助けて。』 「あ、また!」 ぼたんは、声の聞こえた方へ視線を向けた。 「聞こえただろう?飛影。今の子供の声。」 「?」 子供の声など聞こえただろうか? 飛影は、刀を構えたままで上へと視線を向けた。 上には気配を消してはいるが、妖気を感じる。 しかも一つではない。 巫蠱とした妖怪ではないだろうか。 飛影は面白そうに口もとを上げた。 「おい、女。」 「だから、女じゃなくて、ぼたんだって言ってんだろう!?」 「…チッ。命が欲しければ、このまま帰れ。」 そう言うと飛影は、ぼたんの首筋から刀を降ろした。 ぼたんの前を通り過ぎると、迷う事なく階段を上り始めた。 「ちょ、ちょいと待っておくれよ!飛影ってば!」 完全に腰が引けてるぼたんは、くつっつくようにして飛影の背中についた。 飛影はチラリとぼたんへと視線を走らせた。 見るからに弱い奴が、何をしているのか。 「幽助はどうした?」 「へ?幽助?さぁねぇ・・・ここの所、指令はないからねぇ。」 「フン。やはり、貴様は救えん奴だな。」 幽助と共にいれば、まだ話しは分かると言うのに。 体がなまっている飛影にとっては、この上ない相手。 ぼたんがどうなろうと、正直な所は知ったところではないのだが。 後々面倒な事になっても、それはそれでごめん被りたい。 「ちょっと、飛影、どう言う意味なのさ!」 「・・・さぁな。」 触手が飛影とぼたんに向かって伸びてきた。 飛影は咄嗟にぼたんを後へと突き飛ばし、触手から逃れた。 だが、ぼたんの後は階段。 無論、ぼたんは足を踏み外して、そのまま転落した。 「危ない!」 そんな声が聞こえたような気がしたが、今のぼたんにはそんな事を気にしてる余裕はなかった。 体にくる衝撃に耐えるように、目をぎゅっとつぶって、奥歯を噛みしめた。 だが、行くら待っても痛みの衝撃は来ない。 ゆっくりと目を開けてみると、目の前に超美人な顔。 もとい、蔵馬の顔。 「く・・・蔵馬?」 驚く程のぼたんの間の抜けた声。 蔵馬は重いため息を一つつくと、横抱きにしたぼたんを下へと降ろした。 腰が抜けてしまったぼたんは、その場に座り込んでしまった。 「すまないねぇ。蔵馬。助かったよ。」 「言いましたよね、迷惑をかけないでくださいって。」 「聞いたけど…。」 「こんな所に、何の用があったんですか?貴方だって、霊界の者であればこれだけの邪気まみれの妖気に気付かないわけないでしょう?死にたいんですか?そうしたいのであれば、止めはしません。ですが、それは俺のいないところでお願いします。なんで、黙ってるんですか?黙ってても、わかりませんよ。聞いてるんですか?大体、貴方と言う人は、後先を考えずにっ」 「フン。今日はやけに饒舌な事だ。」 蔵馬の言葉を遮るように、飛影が触手から逃れてぼたんの脇へと着地した。 右側には蔵馬。 左側には飛影。 一見してみれば、二人の騎士に守れてるかのようなぼたん。 だが、ぼたんの心境としては、蛇に睨まれた蛙状態だった。 何故かはわからないが、蔵馬が口を挟む間も与えない程に質問責めしてくるし。 飛影は、相変わらず何を考えてるのかわからない。 いや、確実にあれは事故に見せかけて殺そうとしたはずだ。 ぼたんは背中にいやな汗が流れた。 出来ればこのポジション、やめて欲しい。 今のぼたんの切実な願いだった。 「そう言う貴方こそ、俺が来るのわかってて、後に逃がしたのではないですか?」 「知らん。」 え? 飛影が逃がした? もしかして守ってくれた・・・とか? ぼたんは信じられないと言うように飛影の事を見た。 そんなぼたんの視線を受けて、飛影は射殺すかのように睨み付けた。 「なんだ、その目は。」 「い、いえ、なんでもありません。ハイ。」 ぼたんは慌てて、飛影から視線を逸らした。 ともかく、今はへたな事を言って飛影を怒らせるのはよくない。 さすがのぼたんにも分かる事だ。 ぼたんはチラリと蔵馬の事を見つめた。 「なんですか?」 「なんで、蔵馬はここにいるんだい?」 「貴方こそ、どうしているんですか?」 質問を質問で返す嫌な奴。 何気なく飛影の言葉を思い出して、ぼたんはキョトン…と蔵馬の顔を見つめてしまった。 もしかして、飛影の言う『奴』と言うのは、蔵馬の事ではないだろうか? 「飛影、もしかして…さっきのって蔵馬の事?」 「他に誰がいる。」 キッパリと断言されて、ぼたんは苦笑した。 なるほど。 さすがの飛影も、蔵馬の口には敵わないとみえる。 なんとなく飛影が可愛く思えて、ぼたんはクスクスと笑ってしまった。 急に笑いだしたぼたんに、気でも触れたかと、蔵馬と飛影は同時にぼたんの事を見つめた。 「「・・・。」」 ジッと二人に見つめられて、ぼたんは慌てて笑みを引っ込めて俯いた。 今はそんな事をしてる場合ではなかった。 下手な事をして、殺されても困る。 だが、笑いを引っ込めても二人からの視線は注がれたままだった。 ぼたんは、恐る恐る顔を上げて二人の事を見上げた。 下から見上げるような形になったぼたんに、二人は一瞬息を飲んだ。 「?なんだい?二人して。」 「・・・チッ。」 「いえ、別に。」 蔵馬と飛影は互いに視線を合わせると、フイと顔を逸らした。 意味が分からないぼたんは、コクンと首を傾げた。 『助けて!お姉ちゃん!助けて!』 また、少年の声がぼたんの耳に届いた。 ぼたんは顔を上げると、声の聞こえた方へと顔を向けた。 「また、やっぱり誰かいるんだ!」 ぼたんは、まるで何かに心を捕らわれたように走りだした。 触手が無数にはびこる中へと。 まるで、無防備に。 自ら入り込んで行ったのだ。 「ちょっと!」 「バカな女だ。」 飛影と蔵馬は、慌ててぼたんの後を追いかけたが、触手が行く手を塞ぐ。 声など聞こえていない。 ただ、ひたすらに邪気が呼び寄せるかのように、その周辺を覆っているだけだ。 おそらく、ぼたんは・・・。 蔵馬にしては珍しく、顔を顰めると、触手を避けながら暗い先を見つめた。 「疑似餌…ですね。」 「チッ。面倒な事、起こしやがって。」 「どうします?飛影。」 飛影と蔵馬はすでに姿が見えないぼたんの行った先を見つめた。 このまま入れば、敵の思うつぼ。 だが。 このままにしておくことも出来ないだろう。 飛影は、愛刀を抜刀すると上着を脱ぎ捨てた。 どうやら答えは決まったようだ。 蔵馬も同じと言うように、髪の後に隠してあった一輪の薔薇を取り出すと、その薔薇へと大量の妖気を送り込んだ。 美しいバラは、みるみるうちに長い鞭へと変化を遂げた。 「薔薇鞭ッ!」 しなやかな鞭を一度振るうと、棘に触ったもの全てが、まるで鋭利な刃物で切られたかのように、切り裂かれた。 「俺の邪魔だけはするな。」 「わかりました。」 蔵馬と飛影は、暗闇へと飛び込んで行った。 |
気に入って頂けたら、ポチッ!↓と押してやってください m(_ _)m
