| 幸 せ の 意 味 を 探 し て | |||
| 〜 第五話 『 母の勘。 』 〜 | |||
「蔵馬って…頑固だったんだねぇ。初めて知ったよ。」 「それは、光栄です。」 今日も今日とて学校帰り。 蔵馬とぼたんは二人で下校していた。 蔵馬を隣にしながらの、行き交う人々の視線に多少は慣れたものの…。 ふと気が緩めば、飛んでくる嫉妬と言う負の感情の波。 流されないようにするのがやっとだった。 ぼたんは心底疲れたように、肩をガックリ落としながら商店街を歩いていた。 「それで、今日は買い物ですか?」 「…最近、私をからかって楽しんでるじゃないかい?」 「・・・まさか。」 ニッコリと作りました!と言わんばかりの蔵馬の笑顔。 「その間は、なんなんだい…まったく。」 最初は、本当に心配してくれているのかと思っていたぼたんも、日が経つにつれて、違うと思うようになった。 あれからと言うもの、幽助はまったくもって役に立たない。 何回か駆け込んだり、愚痴を零してはみたが、ニヤニヤと笑いながら「からかってるだけだろー。よっ!ご両人!」と言われる始末。 クラスにおいては、すでに公認のカップルのようになってしまっていた。 逆に一緒にいない時の方が、不思議がられる程に。 ぼたんは大きなため息をついた。 「何か悩み事ですか?」 「悩んでるに決まってんだろーが!!誰のせいで、こんなに悩んでると思ってるんだい!」 「悩みなんて物は、自分が考えるから悩むものですよ。悩みたくないなら、何も考えなければいいだけです。普段のあなたのように。」 「ぬわっ!?」 言われた瞬間、ぼたんは拳に力を込めた。 だが、ここで怒っても仕方ない。 蔵馬に敵うわけがないのだから。 ぼたんは怒りを静めるように、数回深呼吸して息を整えた。 「それよりも、買い物するんじゃないんですか?早く行かないと、特売品なくなりますよ。」 平然とぼたんの横を通り過ぎる蔵馬に、ぼたんは心の底から脱力感に襲われた。 蔵馬の弱点と言えば、彼の母親になるのだろうが。 もしもそんな弱点をつけば、その先にどんな地獄が待ってるかわかったもんじゃない。 まったく足を進めないぼたんを不思議に思って、蔵馬はその場に立ち止まって振り返った。 ガックリと肩を落としてるぼたん。 少し虐め過ぎましたかね。 内心苦笑しながら、ぼたんへと近づいた。 どうもぼたん相手だと、ついつい意地悪したくなってしまう。 別に虐めるつもりは毛頭ないのだが・・・。 百面相のように、くるくると変わる表情を見ていると、他にはどんな表情するのかと思ってしまう。 自分の手で、どんどん引き出したくなってしまう。 そして気がつけば、こんな感じに意地悪してしまっている。 「あの。」 「あら、秀一じゃない。」 ぼたんに声をかけようと手を伸ばした瞬間。 少し先にいるのは、まぎれもない自分の母親。 蔵馬は驚きのあまりその場で硬直してしまった。 珍しい蔵馬の態度に、ぼたんはゆっくりと後を振り返った。 「あら、お友達?初めまして、秀一の母です。」 「あ、いやっ、その!おっお久しぶりでっ!!!」 あたふたとしながらも、ぼたんが挨拶をしようとした瞬間。 ぼたんの背中にヒヤリ…と冷たい物が。 どう見ても、植物を何かに変化させたとしか思えない、その妖気。 「あら、どこかで会った事あったかしら?」 不思議そうに顔を傾ける母親に、ぼたんは飛び上がる程に驚いた。 ぼたんは初対面ではない。 あの暗黒鏡の事件の時に、見ている。 だが、人間として会うのは初めての事だ。 それをうっかり忘れていたぼたんは、ついつい「お久しぶり」と言う言葉を出してしまった。 だが、それを出したと同時に、蔵馬から突き刺すような妖気が発せられた。 いや、本当に背中にナイフのような感覚はあるのだが。 今は気にしないようにしよう。 ぺこりと頭を下げると蔵馬の母は嬉しそうに近づいて来た。 「あ、いや、その、えっと、はははははは、初めましてでございまする。お母様。」 「フフフ、面白いお嬢さんね。お名前を聞いても良いかしら?」 な、名前? ぼたんはチラリと蔵馬の事を見つめた。 言っていいのか、一応伺いをたてておかないと・・・。 そんなぼたんの視線を見ていた母親は、苦笑にも綺麗な笑みで微笑んだ。 「あら。もしかして、お邪魔だったかしら?」 「い、いえ!そんな事はっ!!!」 「かわいいわね。顔が真っ赤よ。秀一も黙ってないで、なんとか言いなさい。」 にっこりと微笑む母親に、ぼたんはどうして良いか分からずに俯いてしまった。 蔵馬はぼたんの肩に手を置いた。 「彼女は、クラスメイトの水先ぼたん。転校して来たばかりだから、色々と街案内をね。」 「あら、そうなの?でも、なんで商店街になんか・・・。」 「彼女ご両親がいないから、自炊してるんだって。」 「まぁ。」 ぼたんの事をジッと見つめていた蔵馬の母は、ポンと自分の手を叩いた。 「そうだわ♪」 母親の妙な明るさに、蔵馬は一抹の不安を覚えた。 当然のことながら、家に友達を連れて来た事などない。 幽助以外は。 無論、女友達など母親に紹介もした事がない。 実際にそこまで仲良くなるような友達は作らなかった。 作れば、辛い思いをすることが分かっている。 蔵馬は慌てて、ぼたんの腕を掴むと母親に背を向けた。 「母さん、それじゃ俺達はあっちに用事があるから。」 「ウチに夕食を食べにいらっしゃいな♪」 「えっ!?」 やっぱり。 なんとなく予想は出来ていた。 だが、いざとなると・・・蔵馬は、苦笑を浮かべた。 「か、母さん。水先さんに、迷惑かけちゃうから。そんな急に。」 「あら、あなたに聞いてるんじゃないのよ。ねぇ、ぼたんちゃん♪ぜひ、いらっしゃいな。」 「ぼ・・・ぼたん・・・ちゃん・・・。」 母親の異様な喜びように、めまいを感じた蔵馬。 しかも『ぼたんちゃん』とまで呼ぶ始末。 ここまでくれば、ぼたんが断るしか方法はない。 蔵馬がチラリとぼたんの方へと視線を向ければ、何故か唇を噛みしめて、目がうるうるしていた。 ドクン・・・ 一瞬、鼓動がずれた。 蔵馬は驚いたようにぼたんの事を見つめた。 何故、そんな顔をしてるのか。 それはしっかりと母親にも見えているようで。 「あら、ぼたんちゃん、どうしたの?」 「いえ・・・そんな風に言われたの、久しぶりで。」 無理に作る笑顔に、蔵馬は一瞬魅入ってしまった。 真珠のような零れた雫を、指で拭うぼたんの姿に、夕映えするシルエット。 このままの調子でいけば、ぼたんは断りもせずに、頷くとそう思っていた。 だが。 「ご厚意は、とても嬉しいのですが…ご迷惑はかけられませんので。」 「あら、ウチは一向に構わないのよ?」 「いえ…蔵、南野君は学校中で人気者ですから。それこそ、南野君にご迷惑がかかるので、今回はすみません。」 ぺこりを頭を下げるぼたんに、唖然と見つめてしまった。 まさか、断ると思っていなかった。 だが、ぼたんはニッコリと笑みを浮かべると 「今度、改めて誘って下さい!その時は学校での南野君のお話し、沢山しますね!」 「ぼたんちゃん…。」 その笑顔が、蔵馬から見ても寂しいもので。 本当に申し分けなく思っているぼたんの表情に、蔵馬は自然と口が動いていた。 「俺は別に構わないよ。」 「「え?」」 ぼたんと母親の二人から、問い返されて蔵馬は、自分が今何を口走ったのかと口もとを抑えた。 今、なんて言った? 無意識のように言ってしまった言葉に、ぼたんはあり得ない程の驚きよう。 そして、母親は。 俺からぼたんを奪い去ると、腕を組んでスーパーへと歩き出していた。 「さ!秀一も大丈夫って言ってるのだし、遠慮は無用。何が食べたい?ぼたんちゃん。」 「えっと、その・・・蔵、南野君!!!!」 「ちょ、ちょっと、母さん!!!」 慌てて母親とぼたんを追いかける蔵馬を、幽助と桑原がとんでもないものを見たような表情で見送っていたのを、知りもしない。 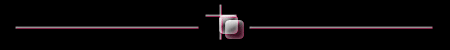 強制的に蔵馬の家へと連れて来られたぼたん。 最初は蔵馬の部屋に通されたのだが、なんとなく落ち着かなく、結局は母親と共に夕食の手伝いをする事に。 蔵馬も部屋にいるわけにも行かず、居間のソファーに身を沈めてテレビへと視線を向けていた。 だが、テレビの音は一切耳には入らず、ぼたんと母親の会話の方に集中するばかりだった。 「え、じゃー秀一ってそんなにモテるの?」 「はいな♪そりゃー、多分、学校で一番だと思いますよ♪」 「えーウチじゃ単なる我が儘息子なのに。」 クスクスと楽しそうに話す母の声。 こんな声を聞くのは久しぶりのような気がする。 だんだんと年齢を積み重ねれば、積み重ねた分だけ、距離が出来るような感覚。 どう接していいか分からなくなっていく不安。 どこまで踏み込んでいいのか、その一歩を踏み出せない臆病な自分。 だが、ぼたんは簡単に母親の中へと踏み込んだ。 純粋に、迷う事もなく。 おそらくはそれが、ぼたんの中にある無意識の行為なんだろう。 蔵馬はチラリと台所へと視線を向けた。 「あら、なーに、秀一。その顔は。」 「随分と楽しそうな話ししてるなって思って。」 「ぼたんちゃん、この子ったら、学校での話しを何もしてくれないのよ。だから私、この子が一日どうやって過ごしたかってわからないの。冷たいと思わない?」 そりゃ…言えないだろう。 ぼたんは冷や汗を掻きながら、霊界探偵の助っ人として一緒に働いている蔵馬を思い浮かべた。 「だーかーら、こうしてぼたんちゃんから聞いてるの♪女の話に、男は入って来ないで頂戴ね。」 「参ったな・・・ホントに。何を言われるか、ヒヤヒヤしちゃうよ。」 「ひっ!?」 ほんの刹那、ぼたんを睨む蔵馬の視線。 余計な事はしゃべるなよ・・・と言う視線。 ぼたんは、黙って何度も頷いた。 まだ、死にたくありませ〜ん(T_T) 母緒に見えないように一睨みしてから、再びソファーへと戻った蔵馬。 それを見届けるように、蔵馬の母親は視線を蔵馬へと向けたままで小さく笑みを漏らした。 「秀一ね、親の私が言うのもおかしいんだけど、生まれてから『我が儘』って事を言ったことないの。反抗期もなかったし。」 「寂しいんですか?」 俯いた母親の顔を見て、ぼたんは自然と言葉が零れ落ちた。 その言葉にハッとした顔した母親は、無理矢理に笑みを浮かべた。 「贅沢な話しなんだけどね。」 「そんな事ないですよ。きっと、み、南野君はお母さんの事が大好きなんだと思います。」 「え?」 それは確実。 蔵馬は自分の命と交換してまでも、この人の事を助けようとしたのだから。 それは、今まで育ててもらった恩だと言っていたけど。 極悪非道で冷静沈着と言われていた、大盗賊の妖狐蔵馬をそこまで改心させた、たった一人の人間。 それが霊界の中でも、どれほどまでに話題になった事か。 ぼたんはコエンマがしきりに不思議がっていたのを思い出して、自然と笑みが浮かんでいた。 そして、しっかりと母親の目を見つめた。 「それは、私が保証します。」 ふと蔵馬の方に視線を向ければ、こちらの会話に聴覚を集中してるのか、手に持つ雑誌のページが一向に動かない。 そんな人間味のある蔵馬。 なんだかんだと口ではキツイ事を言ってはいるが、根本は優しい。 必要以上に監視されているようで、頭に血が上っていた時は考えもしなかったが。 今こうして冷静に見てみれば、分かる。 「蔵馬は、人の痛みを自分の痛みのように感じてしまう人だから。だから、心配です。いずれ蔵馬の中で大事な人が命の危険にさらされた時、簡単に命を投げてしまわないか。」「ぼたんちゃん…。」 「どんな命でも、命は命です。軽いも重いもないんです。自分の命以上でも以下でもないんです。みんな同じに大切な命なんです。蔵馬は、守るべき人がいるのであれば、決して命を捨てるなんて選択、あってはならないんです。でも、蔵馬はきっと無意識でそれをやってしまうと思います。私は…私は、それが一番怖いです。」 ぼたんは、俯き手元のサラダボールを見つめた。 中途半端に混ざっているドレッシングを、ゆっくりとかき混ぜ合わせる。 幽助がいて、桑原君がいて、飛影がいて、蔵馬がいてそれが一つの素材になるかのように、それぞれの主張が上手い具合に歯車としてかみ合ってる。 それのどれが欠けてもいけない。 だが、飛影や蔵馬に関しては、元々妖怪と言うのもあるからか。 生と言う事に対して、執着がない。 強ければ、生きる。 弱ければ、死ぬ。 そう言う世界で生き抜いて来た二人を、安穏とした霊界で過ごして来た自分が理解しようとするのは無理がある。 どれだけ傷つき。 どれだけ仲間を亡くし。 どれだけ苦渋を飲んだかしれない。 悪党として名の通ってる二人ではある。 でも、ぼたんの中ではそれでも、簡単に命を捨てる事だけはして欲しくない。 命は、万物平等にたった一つしかない。 いくら転生が出来るとは言っても、それはもう「蔵馬」や「飛影」ではない。 同じ魂を持つ、別の人になってしまう。 今いる二人には、どんなに時が過ぎ去ったとしても、二度と出会う事はない。 魂を扱う仕事をしてるからか、特に強く感じてしまう。 ポタン・・・。 「あれ。」 ぼたんの目から、涙がこぼれ落ちた。 「ぼたんちゃん。」 「あれれ?なんでだ?お母さん、これにタマネギでも入れました!?」 必死に涙を止めようとするも、ぼたんの瞳から次から次へと涙が零れ落ちた。 蔵馬の母親は、手を止めてぼたんの肩にポンと優しく手を乗せた。 「ありがとう。私の息子をそこまで心配してくれて。ぼたんちゃんが秀一のお友達で本当に良かった。ぼたんちゃん、ウチの秀一の事、好き?」 「あ、いや、べ、別に深い意味じゃないんです!!」 真っ赤になりながら否定するぼたんに、一瞬キョトンとした母親は、数秒後にクスクスと笑い出した。 そんな母親を不思議そうに見つめるぼたん。 「ぼたんちゃん。」 「は、はい。」 「お友達でもいいから、いつまでも秀一の傍にいてあげてね。お願い。」 きゅっとぼたんの手を握ってきた母親に、ぼたんは言葉につまり俯いてしまった。 はい・・・なんて軽々しく言えない。 でも、いいえ・・・なんても言える訳がない。 ぼたんは握られている手に、微かに力を込めてから、その手から微かな霊力を母親へと送り込んだ。 突然の霊気に、蔵馬は驚いて振り返った。 ぼたんの周りの金色の霊気が、母親をまるで包み込むかのように見えた。 「!」 苦笑している母親の顔を見つめるぼたんの表情に、思わず蔵馬は息を飲み込んだ。 慈愛に満ちた聖母のような、そんな暖かな眼差し。 「大丈夫です。蔵馬には、幽助もいるし、桑原君もいます。みんな、蔵馬から離れるなんて事ないですよ。みんな、大好きですから、蔵馬の事。」 最初は苦笑気味だったぼたんの表情が、最後には、本当の笑顔に変わっていた。 自信に満ちたその表情。 誇りを持ったような表情に、蔵馬の母親は安心したように微笑んだ。 「ありがとう。幽助君って浦飯君の事かしら?」 「そうそう。浦飯幽助。」 「まぁ、彼ともお友達なの?」 「あ・・・えーっと、共通な・・・?」 にゃはは〜んと、猫顔になったぼたんは、ツーと冷や汗を感じた。 先程までの聖母のような感覚が嘘のように表情が変わるぼたんを見て、蔵馬の目に優しさを宿した。 本当に見てて飽きない子だな。 蔵馬はソファーに沈み込んで、目を閉じた。 今、自分が出ていくのは野暮ってものだ。 ほんの少しだけ目を閉じるつもりだったのだが、すっかり安心してしまったように眠ってしまった事実に、蔵馬は母親に起こされてから知る事実となる。 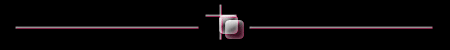 おまけ 「さ、秀一もぼたんちゃんも沢山食べてね。」 「はーい。いっただきま〜す♪」 「うん、母さん。」 蔵馬の横にぼたん。 蔵馬の前に母親。 そんな座り方で夕食を囲んでいたある時 母親は、急に首を傾げた。 「どうしたの?母さん。」 「ねぇ、秀一。なんで、あなた『クラマ』って呼ばれてるの?」 「「えっ…。」」 二人の箸が同時にピタッと止まった。 「どうしたの?二人して固まって。」 「あ、あだ名だよ。あだ名。」 「なんで『クラマ』なの?」 「な、なんでって…。」 珍しく蔵馬が言葉を探してる。 こんな蔵馬を初めてみたぼたんは、慌てて横から口を出してしまった。 助け船のつもりだったのだが。 「あ、あ、あ、あ、そうそう!体育の時間の時に、すごい身軽でみんなで「鞍馬天狗」みたいだねぇって話しなって、それで。」 「あら、そうなの。それでぼたんちゃん、途中から「鞍馬」って呼んでいたのね。」 あちゃー。 ぼたんは蔵馬の視線から逃げるように、顔をそむけた。 チラリとぼたんに視線を向けた蔵馬。 すでに問題は解決したかのように、母親は食事を再開して、テレビへと神経を傾けていた。 そんな母親の様子を見てから、蔵馬は食事をするフリをしながらチラリとぼたんを睨み付けた。 「貴方って人は。」 「ごめんよ〜。」 「いつ、俺が「鞍馬天狗」になったんですか。」 「はぅ・・・すみません。」 ヒソヒソと二人だけで話す蔵馬とぼたん。 視界の端に入れていた蔵馬の母は、にっこりと笑みを浮かべた。 それはそれは、満足そうな。 幸せそうな。 そんな笑みだったとか。 |
気に入って頂けたら、ポチッ!↓と押してやってください m(_ _)m
