| 幸 せ の 意 味 を 探 し て | |||
| 〜 第六話 『妖猫・クロム 』 〜 | |||
ぼたんが、霊界探偵の助手として決まった数日後。 人間界での生活をする為に、プチ引っ越しの用意をしているぼたんが知らない間に、この話しは遡る。 霊界。 コエンマは、執務室で大量の書類に済み印を次から次へと判子を押して行く。 それは本当に目を通してるのかと疑いたくなるほどの速さ。 だがそこは腐っても、エンマ大王の息子。 長年している仕事故の見なければいけない場所と言うのを把握している。 だからこその早業なのだが。 そんな忙しい最中、コエンマの扉をノックしてくる者がいた。 「コエンマ様、誰か来ましたよ。」 「それを確認するのが、お前の役目だろうが、バカタレ!!」 暢気なジョルジュに微かに怒りをぶつけながらも、コエンマの手は止まることがない。 だが。 「特防衛隊(略:霊界特別防衛隊)です。」 その声に、コエンマは手を止めた。 特防隊はわかる。 だが、若い声。 それは特防隊のトップの人材でない事は明白だった。 そんな奴が、コエンマに直接会いに来ると言うこと自体が珍しかった。 本来なら、特防隊の上司と共に来るのが筋と言うものだからだ。 「入れ。」 コエンマの声で、重々しい扉がゆっくりと開いた。 そこから顔を覗かせたのは、まだ見た目は若い。 人間界で言えば17才程度の青い髪の少年が入って来た。 左胸には一番隊の隊章が光っている。 コエンマは、一つため息をつくと肩か力を抜いて、ゆったりと背もたれに背を預けた。 「久しぶりじゃの、葵。」 「ええ。また霊界探偵をコリもせず雇うとか。」 前の霊界探偵の一件を知っている者だからこそ言える言葉。 コエンマは、言葉につまり目の前の葵を睨んでしまった。 「そんな嫌味を言う為に、わざわざ来たのか、お前は。」 「僕もそんな暇じゃないですよ。今日は、コレを渡しに来たんです。」 そう言われてコエンマの机の上に置かれた一つのスーツケース。 何が入っているのか? コエンマは不思議そうに葵とスーツケースを交互に見つめた。 ニッコリと特有の笑みを浮かべた葵は、スーツケースに手を掛けた。 「噂によると、水先案内人の女の子が助手を務めるって話しじゃないですか。」 「ああ、まぁな。あいつなら、きっと大丈夫だろうと思ってな。」 「だから、これを開発させました。」 ケースが開かれると、中には7つの道具が入っている。 一つ一つを手に取るコエンマに、葵はニッコリと笑みを浮かべた。 霊透眼鏡、妖気計、霊撃輪具、イタコ笛、目印留…などの開発に、かなり急がせた感がある。 だから、一つだけ弱点があった。 それは 「これらは、霊力が高くないと扱えない代物です。」 「霊力が?どれほどの者なら扱えるもんなんじゃ?」 「そうですね…。」 葵は考え込むように、顎に手を持っていき、チラリと天井を見上げた。 そこに思い浮かぶは、自分の幼馴染みの顔。 その子を守る為に作らせたと言っても過言ではない。 「高等心霊術が出来る程度の霊力の持ち主なら。」 「・・・お前、助手が誰だか分かって言ってるだろ。」 コエンマの目はスーっと細くなった。 さぁ?とあくまでシラを切り通す葵。 互いの睨み合いに、隣で控えていたジョルジュがオロオロしながら二人の事を見守っていた。 このまま喧嘩にでもなったら。 葵のぼたんへの溺愛振りは、本人は知らないとは言え、有名である。 ぼたんにとっては、兄のように、家族のような存在、それが葵だ。 それは葵も同じ事で。 いや、葵の場合はそれ以上の感情もあるかもしれぬのだが。 コエンマは黙って葵を見つめたまま、小さくため息をついた。 「お前、開発技術を個人的に使用して良いと思っとんのか?」 「個人利用なんて、酷いですね。開発段階だと言ったじゃないですか。これも一つの実験事例として、こちらとしても結果が得られる利点があるんですよ。」 「だがな。」 「ともかく、これの使用をお願いしますね。それじゃ。」 「あ、おい!!!葵!!!!」 コエンマの静止の言葉も無視して、葵は部屋を出て行ってしまった。 机の上に残された霊界七つ道具。 その中の霊撃輪具を手に取った。 指にはめた瞬間に、霊撃輪具に霊気を強制的に吸い上げられる感覚。 「どわぁ!!」 「ど、どしたんですか、コエンマ様!!」 あまりの霊気に、コエンマは咄嗟に霊撃輪具を外して投げつけた。 なんていう物を…。 強制的に霊丸が打てるものと言うのか。 だが、どのサイズを見ても一人の特定の人物に作られたとしか思えないような代物。 まったく。 コエンマはケースを閉じると、それを人間界に行く支度しているぼたんの元へと送ったのである。 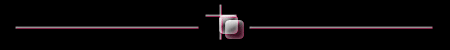 「よし、これで大丈夫だね。」 「いつもすみませんねぇ、ぼたんさん。」 目の前には小さな妖怪。 よく言われるのは使い魔と称される妖怪だ。 妖怪だろうと人間だろうと、怪我している者に対してはぼたんは分け隔て無く、治療を施す。 そんな事を昔から続けていたからだろう。 いつしかぼたんの家の周りには、そんな命を救ってもらった妖怪が集まるようになっていた。 ぼたんの治療を面白くなさそうに、屋根の上から見つめている一対の光る目。 長い尻尾をプラプラと揺らしながらも、何も言わずに見つめる妖猫の男の子。 もちろん、この猫も怪我している所をぼたんに救ってもらい、それ以来ぼたんの家の屋根に住み着いている者の一人だ。 「本当にぼたんは誰にでも優しくし過ぎるんだよ。」 少年特有の声に、ぼたんは困ったように笑みを浮かべた。 「誰かが怪我していたら、助けるのは当たり前だろう?」 「そのウチにそう言う罠を仕掛けてくるバカが出て来ると思うよ。そーなったら、ぼたんはすぐに食べられちゃうんじゃない?」 うーん・・・。 言われてみれば確かに。 それでも、目の前で苦しんでいる者を見て見ぬ振りなんてことは性格上出来ないから。 その時は・・・ 「その時で覚悟するさね。」 「ふーん。後に残された者の事は考えないで、自己満足で死ぬんだ。」 「え?」 ぼたんが顔を上げると妖猫は不満そうに頬を膨らませて、顔を逸らしていた。 なんとも可愛い表現じゃないか。 ぼたんはクスクスと笑い出してしまった。 「な、なんだよ。」 少し顔を赤らめた妖猫が、チラリとぼたんを見つめた。 だが、睨む事はしない。 あくまで優しさの上での視線だった。 この当たりを知っている妖怪ならば、この妖猫がこんな態度を取るのは珍しいと思うだろう。 それほどまでに、悪戯好きで、色々と悪さもしてきた妖猫なのだから。 だが、ぼたんが人間界に常駐するようになってからは、悪戯も見事にすっかり辞めていた。 余ってる時間の暇つぶしとして悪戯していたのだ。 遊び相手がいれば、暇がない。 だから悪戯はしないと…あくまで単純な行動。 「そんな罠にはかからないと思うよ。」 「なんで、そんな事を言えるんだよ。」 ぼたんの言葉に反論するかのように、妖猫がぼたんの事をみれば、ぼたんは妖猫の事を指差していた。 「な、なんだよ、その指。」 「だって、あんたがいるじゃないさ。そんなの、寄ってくる事なんて無理だろ?」 「なっ…!!」 暗に守ってくれてるんだろう?と言われてるのと一緒で。 ぼたんは、ゆっくりと座っていた膝を立たせると、空に向かって大きな伸びを一つした。 「学校でも家も、いつもいるもんね。上に。」 「・・・そう言えば、あの妖狐には気をつけた方が良いと思うよ。」 「妖狐??」 普通に言われてぼたんは、頭に思い浮かぶ知り合いが思い当たらない。 なんだろう?と頭を悩ますと、妖猫はあからさまに深いため息をついた。 「蔵馬だよ。妖狐・蔵馬。あいつは魔界でもここ人間界でも、妖怪の中じゃ、良い噂なんか聞いた事がないからね。」 「蔵馬が?んー…まぁ、盗賊だって事は知ってるけど、それも昔の話しだろ。」 「昔だろうと、今してなくても、その要素は奴の奥底にはあるって事なんだよ。ぼたんはさぁ、少し警戒心がなさ過ぎなんだよ。」 警戒心・・・ねぇ。 彼なりに心配してくれてるのだろう。 ぼたんは、妖猫の頭を優しく撫でると、妖猫は気持ち良さそうに目を細めた。 「蔵馬なら、大丈夫。」 「だから、どこにそんな確信があるんだよ。」 「うーん…女の勘って奴さね。」 「うわぁ、一番頼りにならねぇ。」 ポンポンと妖猫とぼたんとの漫談のようなやりとりに、周りの妖怪も入る事が出来ずに黙って聞いている。 だが、ぼたんを心配するのはみんな同じ。 小さな妖怪達はぼたんの肩や頭によじり昇った。 「ぼたん殿、笑い事ではないでござる。」 「猫殿の言い分、どうか聞いて下され。」 口々に言ってくる妖怪達に、ぼたんは少し困ったように苦笑した。 そんな和やかな雰囲気が一瞬にして、消え去った。 妖猫が屋根から飛び降りると、ぼたんを背に隠すように立ち上がった。 全員が一斉に殺気だつ。 ぼたんは意味が分からずに、全員の視線の先へと視線を向けた。 「おや、蔵馬じゃないか。どうしたんだい、こんな夜に。」 「こんばんは。お邪魔みたいでしたね。母ーさんにコレを貴方に持って行けと言われてね。」 蔵馬の手に持つタッパー。 どうやら何かのおかずが入ってるのだろう。 ぼたんは嬉しそうに、蔵馬に近づこうと足を一歩前に出そうとした。 だが、妖猫によってそれは敵わなかった。 「ちょいと。」 「ねぇ、妖狐蔵馬さん。何、企んでるの?」 「企む?意味が分からないですね。君は?」 「・・・俺は妖猫のクロム。」 ぼたんは驚いたように妖猫の事を見た。 何故なら 「あんた名前あったんじゃないか。」 今の状態にはそぐわない、ぼたんのノホホンとした言葉にクロムは苦笑しながらぼたんの事を見た。 「まぁね。」 「申し分けないけど、君達が想像しているような事はない。」 だが、蔵馬は一歩も動こうとはしなかった。 ジッとクロムを見つめる。 まるでぼたんを守るかのようなクロムの表情。 蔵馬でも気付かない程に、蔵馬はクロムの事を睨み付けていた。 「おー怖い怖い。ぼたん、やっぱりこんな奴の傍にいるべきじゃないよ。」 「だーかーらー、探偵の助手として」 ぼたんの言葉を遮るように、クロムはぼたんの両手をフワリと包み込んだ。 「どんな理由にしても、ぼたんを危険だと分かってる状態で、誰が手放すかよ。」 「ぼたん殿。ここは妖猫殿の言葉を信じてくだされ。」 口々に妖怪達に言われて、ぼたんは少し困ったような表情をしたが、しばらくするとすっといつものヘラヘラしたぼたんらしくない表情になった。 それは真剣な表情と言うのか。 ぼたんは、クロムが包む込む手をやんわりと、離した。 「みんな、心配してくれてありがとよ。でもね、蔵馬はみんなが思ってるような人じゃないんだよ。ちょっと意地悪な所もあるけど、すごく仲間思いな人なんだよ。」 「・・・。」 まさかぼたんからそんな言葉を聞くとは思っていなかった蔵馬。 あまりの驚きに目を見開いてしまった。 ぼたんは、クロムの頭を優しく撫でると、まるで母親のように言い聞かせた。 「蔵馬は私の大切な仲間なんだ。だから、仲間の事を悪く言うのは辞めておくれ。悲しくなっちまうだろう?」 「ぼたん…でも、俺。」 「クロムだって、私にとって大切な人なんだから、誰かに悪く言われれば、悲しくなるんだよ?」 「俺の事、大切?」 「当たり前だろう。」 「うん!」 クロムは嬉しそうに尻尾を振ると、無邪気な子供のような表情を作った。 やっといつも通りのクロムに戻った事で、ぼたんは妖怪達の輪の中からでて蔵馬へと近づいた。 「嫌な思いさせちまって、悪かったね。」 「いえ。飛影から話しは聞いてましたが、これがあなたの取り巻きですか。」 コレ呼ばわりされた妖怪達が一斉に蔵馬の事を睨み付けた。 だが、蔵馬の一睨みでまるで蜘蛛の子を散らすかの如くに、逃げてしまった。 残ったのは、妖猫のクロムのみ。 「ぼたん、すぐに奴から離れろ。」 突然に妖力を爆発的に上げたのはクロム。 蔵馬はとっさにぼたんを自分の背へと隠した。 「離れて下さい。」 「でも。」 「今の彼には、きっと言葉は通じません。」 小さな二人の会話。 クロムの怒りは、頂点に達した。 何か切れるような音と共に、突然蔵馬へと攻撃を仕掛けた。 蔵馬は手に持ったタッパーを離すと、後にいたぼたんを抱え込んでその場から跳躍した。 クロムのツメは、まるで鋭利な刃物のように、その場がえぐり取られる。 あんな物が当たれば、肉はおろか骨までもっていかれるだろう。 ぼたんを横抱きに、少し距離をとった蔵馬はゆっくりとぼたんをその場に降ろした。 「蔵馬。」 「心配いりませんから。」 まるでぼたんを安心させるような蔵馬の笑み。 それでも不安げなぼたんの表情を見て、蔵馬は自然に手が出て、フワリとぼたんの頭に手を乗せた。 ポンポンと子供をあやすように、軽く叩くと、最後に前髪をくしゃりと撫でた。 「くらっ」 「ぼたんに触るなぁぁぁぁ!!!!!」 蔵馬とクロムの戦いが突如始まってしまった。 |
気に入って頂けたら、ポチッ!↓と押してやってください m(_ _)m
